吃音に悩む国王が、世界を前に声を発するまでの道のり――。
映画『英国王のスピーチ』は、英国史に残るジョージ6世の実話をもとに、言葉に縛られた一人の男の「再生」と「友情」を描いた感動作です。
言葉に詰まりながらも、誰よりも真摯に国民と向き合おうとする姿に、私たちは何を感じ、何を語るべきなのか――。
本作の深いテーマや心震えるセリフの数々を、映画と向き合い続けた13年の視点で、徹底解説いたします!
作品情報
- 原題:The King’s Speech
- 監督:トム・フーパー
- 脚本:デヴィッド・サイドラー
- 主演:コリン・ファース、ジェフリー・ラッシュ、ヘレナ・ボナム=カーター
- 公開年:2010年
- ジャンル:歴史ドラマ、ヒューマン
あらすじ
幼いころから吃音に悩んできた英国王子アルバート。
王室の公務でもまともにスピーチができず、内向的で引っ込み思案な性格に悩まされてきました。
兄のエドワード8世が王位を放棄し、アルバートは国王「ジョージ6世」として即位しますが、第二次世界大戦の足音が迫る英国では、国民を勇気づける“国王のスピーチ”が必要とされていました。
そんな中、妻エリザベス王妃の尽力により出会ったのが、風変わりな言語療法士ライオネル・ローグ。
型破りなセラピーを通じて、ふたりは少しずつ心を通わせていきます――。
人生観が変わるポイント
「声に出せない苦しみ」へのリアルな共感
吃音という障がいは、物理的な障害以上に「心の壁」として描かれています。
王という立場でありながら「人前で話せない」という絶望。その中で、恐怖や怒り、羞恥といった感情が丁寧に表現され、視聴者はまるで自分が同じ場に立たされているかのようなリアルさを感じます。
言葉を詰まらせることが、こんなにも辛く、孤独なことなのか――
本作は、表面には見えにくい「声にならない苦しみ」への共感力を深めてくれる映画です。
支え合いの力、そして“対等”な関係の大切さ
印象的なのは、王と平民という立場を超えたライオネルとの関係性です。
上下関係ではなく、あくまで“人と人”。
ライオネルは王を特別扱いせず、ただ「一人の人間」としてまっすぐ向き合います。
「自信を与えること」「信じること」がどれだけ人を変えるのか。
友情が生まれ、信頼が育つ過程に、誰もが心を打たれるでしょう。
「話す」ことの本当の意味とは?
スピーチとは、ただ言葉を並べる行為ではありません。
「相手の心に届くように語る」こと――
そしてそれは、完璧な発音や流暢さではなく、言葉に込められた“真心”が最も大切であると、本作は教えてくれます。
吃音を抱えたままでも、国民の心に響く言葉は伝えられる。
それは、どんな状況でも「声をあげる勇気」が人を導く力になると、深く刻んでくれます。
印象に残るセリフとその意味
「Because I have a voice!」
クライマックスでジョージ6世が放つこの一言は、短くも圧倒的な力を持ちます。
吃音に苦しんだ彼が、ようやく“自分の声”を受け入れ、誇りを持てた瞬間。
ここでいう「声」は、ただの発音ではなく、“自分という存在を表す手段”。
言葉に詰まっても、伝えたい想いがあれば、それは「声」になる――
この台詞に込められた強さと優しさが、涙を誘います。
まとめ
『英国王のスピーチ』は、ただの歴史映画ではありません。
「話すこと」「信じること」「支えること」――人間の根源的な絆と、再生の物語です。
吃音というハンディを抱えた王が、人前で語るまでの勇気。
それを支える友情と信頼の力。
観る者すべてに、自分自身の“声”の意味を問いかけてくれます。
まだ観ていない方には、ぜひ一度その「スピーチの重み」を味わってほしい作品です。
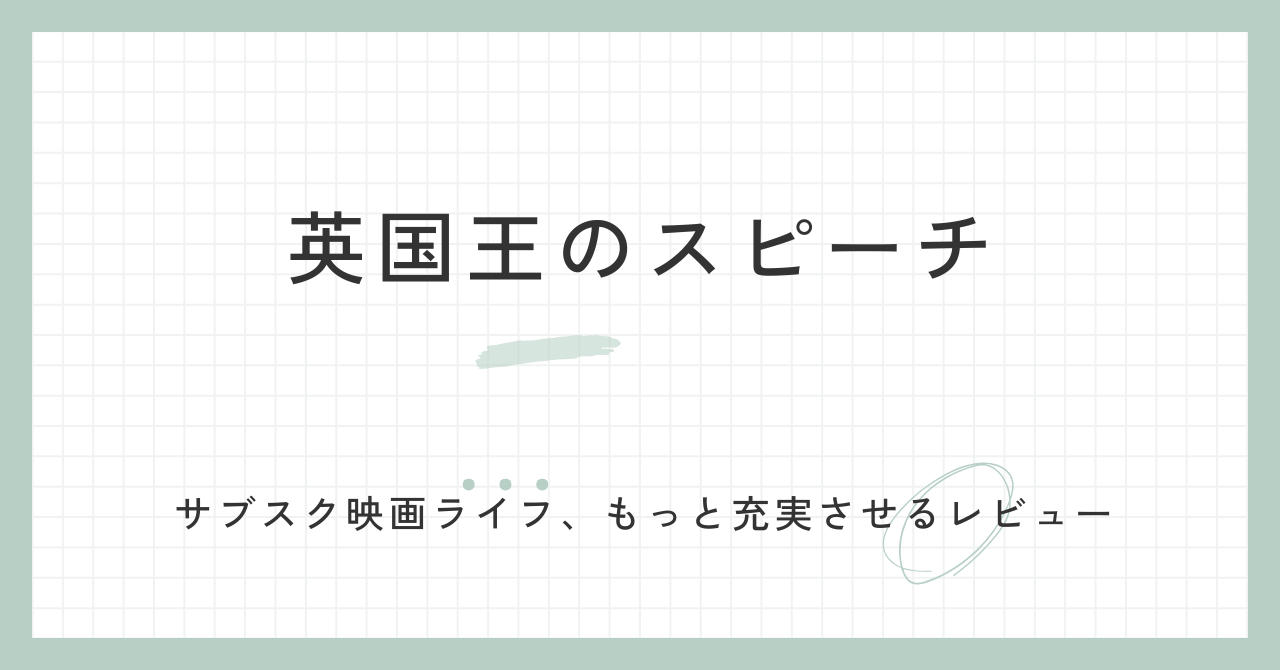
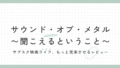
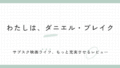
コメント