健常者と障がい者、音楽と沈黙、家族と夢──。
相反するものの間で揺れるひとりの少女の成長を描いた映画『コーダ あいのうた』は、あなたの心を静かに、そして確実に震わせます。
「本当にやりたいこと」と「大切な人たちを守ること」──。
その狭間で悩む彼女の選択に、きっと誰もが自分を重ねてしまうのではないでしょうか?
映画と向き合い続けた13年の視点で、魅力を徹底解説します!
作品情報
- 原題:CODA
- 監督:シアン・ヘダー
- 脚本:シアン・ヘダー
- 主演:エミリア・ジョーンズ、マーリー・マトリン、トロイ・コッツァー
- 公開年:2021年
- ジャンル:ヒューマンドラマ、音楽、家族
あらすじ
舞台はアメリカ・マサチューセッツ州の港町。
主人公のルビーは、漁業を営む家族の中で唯一の“聴こえる子”=CODA(Child of Deaf Adults)です。朝は漁に出て、学校では眠気と闘う日々。
ある日、合唱クラブに入ったルビーは、自分に歌の才能があることを知ります。
音楽教師の後押しもあり、音楽の道を志すようになるルビー。しかし、聴こえない家族には彼女の“歌”が理解できません。
「自分の夢を取るか、家族のそばにいるか」
彼女の心は引き裂かれるような葛藤に包まれていきます──。
人生観が変わるポイント
「愛は言葉を超える」ことを教えてくれる家族の姿
本作の最大の魅力は、聴こえない家族の“無音”の世界が、こんなにも温かく豊かに描かれていることです。
言葉ではなく、視線や手話や表情で伝わる想い。
ルビーの父が、舞台の袖で娘の歌う姿を見て「音が聴こえないのに涙を流す」シーンは、観ているこちらの涙腺も限界を迎えます。
聴こえなくても、感じることはできる。
それは、音楽も、愛も、同じなんだと気づかされます。
「夢を追う勇気」と「誰かのために生きること」の狭間
ルビーが抱える葛藤は、決して障がいを持つ家族との特殊な関係だけにとどまりません。
「親の期待に応えたいけど、自分の夢も諦めたくない」
この葛藤は、私たち誰もが一度は経験する普遍的なものです。
彼女の決断には、強さと優しさの両方が詰まっていて、それが観る者の心を打つのです。
実際のろう者俳優によるリアルな演技
ルビーの家族を演じた俳優陣は、全員が実際に聴覚障がいを持つ“本物”のろう者です。
マーリー・マトリンやトロイ・コッツァー(2022年アカデミー助演男優賞受賞)は、手話だけでなく、体全体で「演技」という表現を完成させています。
そのリアルな表現が、映画全体のリアリティをさらに高め、観客にとって“彼らがどれだけ日常と格闘しているか”をリアルに想像させるのです。
印象に残るセリフとその意味
「もし私が誰かの声になれるなら、それが私の歌だと思う」
これは、ルビーが家族の通訳として育った彼女自身の人生を象徴する言葉です。
“声”というのは、単に音を出すことではありません。“誰かの想いを、世界に届けること”。
彼女が手にした“歌”という表現方法は、まさにその役割を果たすものであり、だからこそ彼女にとって音楽は単なる夢ではなく、「自分自身の生き方」となっていくのです。
まとめ
『コーダ あいのうた』は、音が聴こえる・聴こえないという“違い”ではなく、
「どんな風に愛を伝え合うか」という“心の共鳴”を描いた、優しくて強い映画です。
家族の重み、夢の重さ、そして一歩を踏み出す勇気。
そのすべてがあなたの胸に響くこと間違いありません。
まだ観ていない方には、自信を持っておすすめしたい作品です。
サブスクで観られる今こそ、心震えるこの物語に出会ってください。


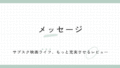
コメント